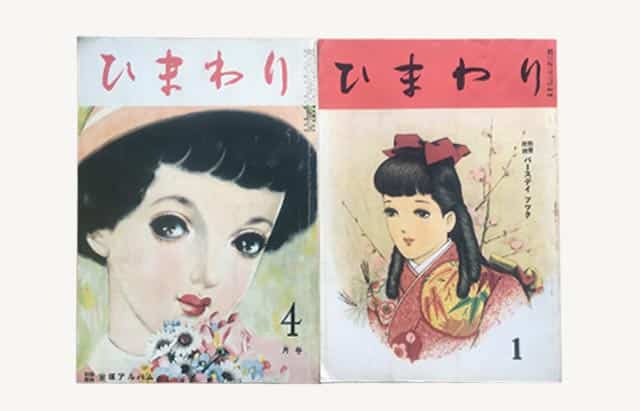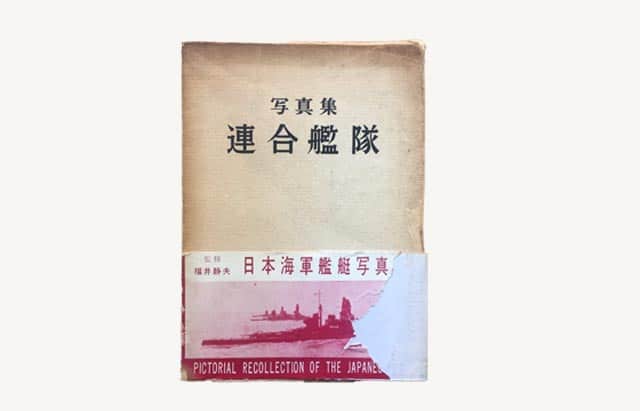古本買取について 本の歴史
![[東京書房の3]買取方法は出張買取、宅配買取、店頭買取の3つからお選びいただけます](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv3.jpg)
![[東京書房の3]買取方法は出張買取、宅配買取、店頭買取の3つからお選びいただけます](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv3_sp.jpg)
![[東京書房の0]東京書房の古本買取なら、送料無料、出張費無料、手数料無料の3つの0を実現](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv0.jpg)
![[東京書房の0]東京書房の古本買取なら、送料無料、出張費無料、手数料無料の3つの0を実現](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv0_sp.jpg)
![[東京書房の100]年間買取実績100万冊以上!出張買取は年間2,000件以上](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv100.jpg)
![[東京書房の100]年間買取実績100万冊以上!出張買取は年間2,000件以上](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv100_sp.jpg)
![[東京書房の0]本を捨てないで!捨てられる本を0にしたい](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv0_2.jpg)
![[東京書房の0]本を捨てないで!捨てられる本を0にしたい](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv0_2_sp.jpg)
![[東京書房の∞]本で得られる知識や笑顔は無限大](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv_infinite.jpg)
![[東京書房の∞]本で得られる知識や笑顔は無限大](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv_infinite_sp.jpg)
![[東京書房の24]メールでのお問い合わせは24時間受付中](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv24.jpg)
![[東京書房の24]メールでのお問い合わせは24時間受付中](https://tokyoshobo.jp/wp/wp-content/themes/tokyoshobo2021/assets/imgs/index/mainv24_sp.jpg)







日本で初めての週刊誌は團團珍問
存在する最古の本は聖徳太子の法華義疏
本の最初は修道院の修道士
本の歴史。
記録する形は、画から文字へ
本の成り立ちをご存知ですか?
知識や情報は、紙などの物理的な媒体に記録し、印刷・複製し、流通してきました。
本の印刷情報の通信手段として言葉や文字を用いるようになって、それを記録し保存する必要があり、そのためにメディアは形を変え、その都度生み出されてきました。
そして現在の代表的なメディアは紙です。紙の技術は、中国から朝鮮半島に渡り、日本に伝来します。そのあと、イスラム諸国に、スペイン、ヨーロッパへと広がっていきました。
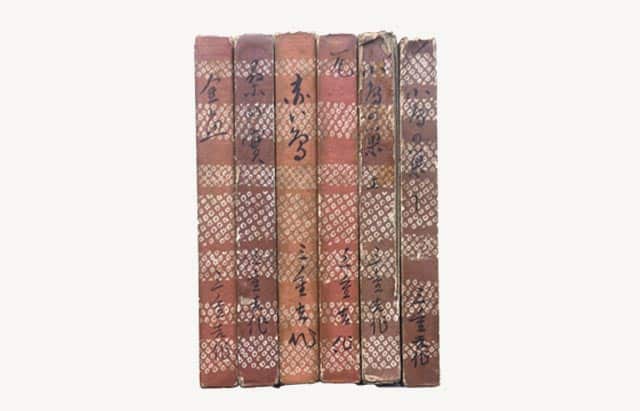
持ち運びが便利に、
ページをめくる楽しみ
中世の時代、知識を保持し、享受するために、図書館が修道会によって建設されます。図書館は書物を独占し、蔵書の目録は時代にとっての宝物。その当時、西暦1500年までに印刷された書物のすべてを、「インキュナビラ」といいます。言語は、ラテン語。意味は、おむつ。印刷術が、その時はまだゆりかごの中にあったから、と言われています。インキュナビラには扉も表紙もなく、巻末を開かざるをえません。結局全部読むことになります。
読書には、非常に不便。読みたいところだけ、読めればいいのに。そんな願いをかなえるべく、袋綴じが開発。冊子状になり、持ち運べて非常に便利に。そうなると、一つの書物では、不特定多数の読者を支えきれません。たくさんの作品が、世の中に生み出されることになります。
その後、グーテルベルクによって印刷業が革新。また、印刷業が発達すると、その都度新しい文字が生まれ、文字の種類が増えると、優れた作品ができ上がります。書物が乱雑に増えていき、一度知識を系統立てて整理するために、辞書が開発されます。辞書ができたのは、啓蒙主義のおかげ。
その後、印刷業が発達・普及したのは、宗教改革のおかげです。思想の移り変わりに対応するため、厚い紙より薄い紙が効率的。装丁ができあがり、横に置くものが縦に保管されるようになります。
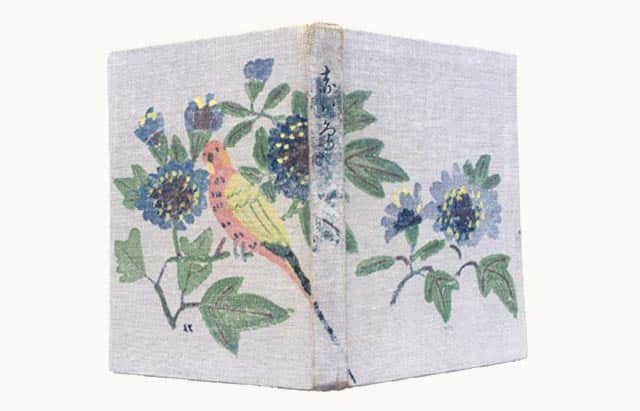
保管する書庫から、
取り出す本棚へ
本のできが良くなると、たくさんの方が欲しがります。ですが、その知識が優れたものであるなら、その対価も高くなります。それでも、知識が、情報が必要という方のために、自分の蔵書を提供しようと考え、文庫が誕生します。小型化が流通し、その後軽量化へと進む産業。
メディアは移って、紙から電子へ。著者の意向を汲んだものではなく、誰もが自由に複製できるようになり、著作物自体に権利がつきます。著作物に権利がつくと、提供する方法が限定され、誰もが情報を発信するようになり、誰もが作り手としての立場になりえる時代になってきました。コピー機がなくなる、そんな時代がくるかもしれません。
だからといって、昔のものに価値がなくなるわけではありません。あまりに希少なものは博物館や国のものとなりますが、流通するにはその理由があり、時代時代の大衆文化は貴重な文化遺産といえます。
誰かが手に取った本をめくってみてはいかがでしょう。自分以外の人もこの本を読んでいると思うと、なんだか奇妙な親近感がわいてきて、別の誰かに貸したくなっちゃうかも。
巡り巡って、あなたの本が、街の古本屋に。意外な書籍が高価買取できる場合も数多くございますので、本の処分、整理をお考えの方はぜひ一度ご連絡ください。